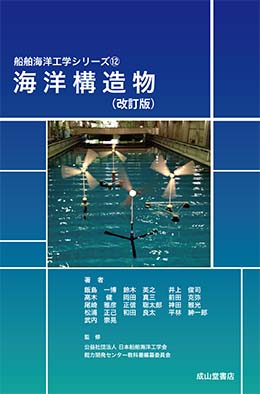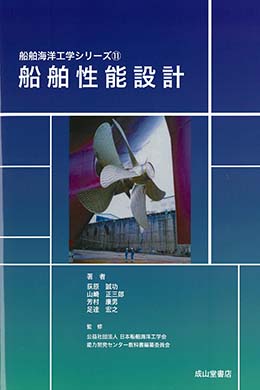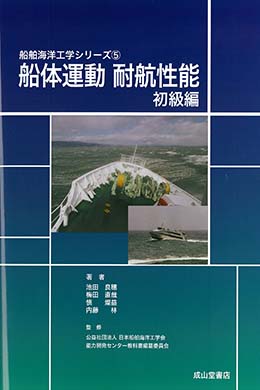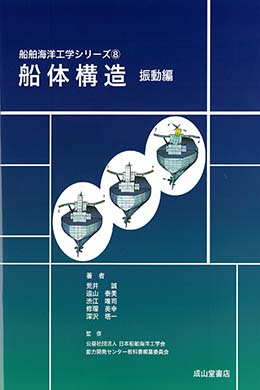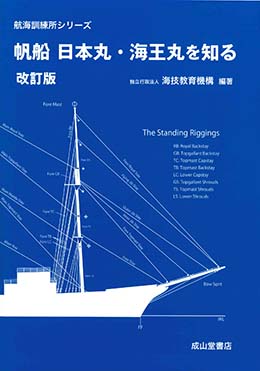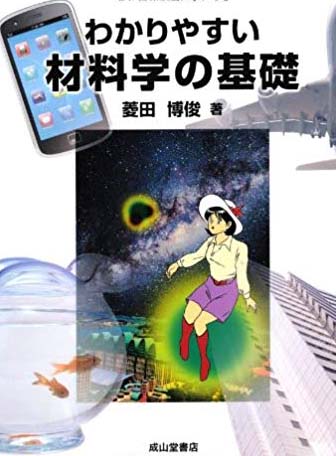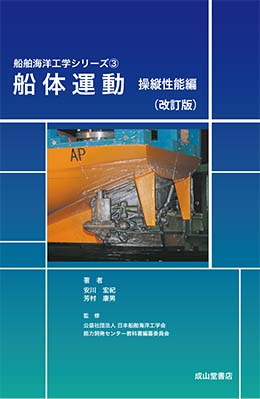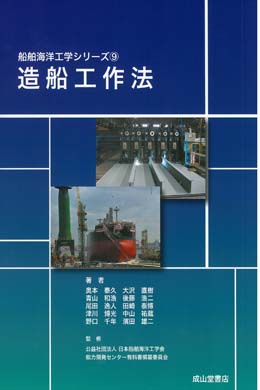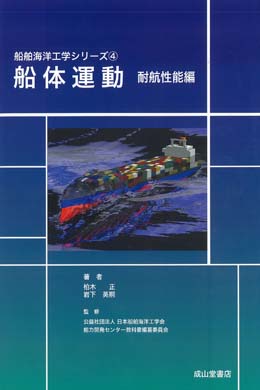海事の書籍紹介
海洋構造物 船舶海洋工学シリーズ12
飯島一博・鈴木英之・井上俊司・高木健・岡田真三・前田克弥・尾崎雅彦・正信聡太郎・神田雅光・松浦正己・和田良太・平林紳一郎・武内崇晃
海洋開発の基礎技術が1冊に! 資源開発、環境対策で注目される海洋開発に用いられる機器や設備を、海洋の波、風、流れ、水圧など厳しい環境下で保持し、安全に機能させるための基盤技術として、海洋構造物の基本的概念から力学的特徴、設計の考え方について紹介する。
【改訂版発行にあたって】
2013年に本書の初版を発行以来、学生・設計者をはじめ多くの関係者にご利用いただいた。そして,10 年を経て改訂のタイミングとなった。10年前の当時、学生でこの教科書を手に取った元学生はベテランに差し掛かる頃である。彼らは10年の間、いろいろな専門書を読……
船舶性能設計 船舶海洋工学シリーズ11
荻原誠功・山崎正三郎・芳村康男・足達宏之
船舶流体力学を基礎とする船舶性能に関する理論を紹介。船体の抵抗成分と船型設計の考え方、プロペラ推進に基づいた船尾形状設計法、スクリュープロペラの特性とその設計法、操縦運動を制御する操縦装置の設計、船舶に装着される省エネ装置の原理とその結果、就航後の船舶性能の解析手法などについて実例を示しながら解説した。
【まえがき】より
近年の船舶系の大学での履修状況は、造船工学に関する基本的あるいは実務的な履修に多くの時間を割くことが難しくなり、その内容は必ずしも以前のような形態がとられていません。また、船舶系の学科の卒業者数が減少し、造船産業……
船体運動(耐航性能 初級編) 船舶海洋工学シリーズ5
池田良穂・梅田直哉・慎燦益・内藤林
耐航性能の初級知識を徹底管理! 荒れた海の中でも船体、機関、積荷などに損傷を受けることなく予定通り航行できる能力を「耐航性能」という。本書では、この船舶の耐航性についての基礎として学んでおくべき基本的な事項、理論的アプローチなどについてわかりやすくまとめた。船舶の耐航性能の初級の知識を徹底整理する上で最適な1冊。
【まえがき】より
大洋を航海する船舶にとって、荒天でも本来の機能を発揮することがもっとも重要である。荒れた海の中でも船体、機関、積荷などに損傷を受けることなく予定通り航行できる能力を耐航性能という。本書では、この船……
船体構造(振動編) 船舶海洋工学シリーズ8
荒井誠・遠山泰美・渋江唯司・修理英幸・深沢塔一
接水振動や防振対策、波浪中での船舶の動的応答についても詳しく解説した振動学の新定番!振動に関する基礎知識、基礎理論から、船体振動問題への応用について学習でき、とくに一般的な振動学の教科書にはない、梁や板の振動理論、接水振動いついては詳しく解説した。
【まえがき】より
大学の機械系学科においては、基礎科目として振動学の講義が開催されており、多くの優れた教科書や参考書が出版されている。本書も振動学の教科書であるため当然のことながら振動の基礎知識をまとめており、既存の書物と共通した内容の記述も多い。しかしながら、本書は船舶海洋工学系の学……
航海訓練所シリーズ 帆船 日本丸・海王丸を知る(改訂版)
独立行政法人 海技教育機構 編
世界最大級の帆船、日本丸と海王丸の仕組みと運航技術を1冊に収録。マスト、帆、ロープの詳細な図解で複雑に見える帆船の構造を理解できる。帆走理論、航法などの専門知識を現役の航海士が丁寧に解説。
【はじめに】より
本書の基になった帆船操典の作成は昭和37年にまで遡ります。当時の日本丸船長であった千葉宗雄教授が主として執筆された原稿をもとに帆船操典の初版を発行し、その後「高所及び帆船作業指針」(昭和38年3月)、「帆船操典(追録)」(昭和41年3月)を加え、昭和42年2月、実習上の便宜を図るため本文と付図の2分冊として発行しました。昭……
港湾倉庫マネジメント−戦略的思考と黒字化のポイント−
篠原正人 監修・春山利廣 著
あなたの倉庫は黒字ですか?
「きめ細かい運営をすれば、日本人ならではの素晴らしい港湾倉庫サービスが実現する」、「荷主の求める物流を的確に、かつ、適正なコストで提供すれば黒字化が達成できる」と語る篠原氏と春山氏。国際競争の厳しさを肌で知る二人が、このような革新を持つことができたのはなぜか。倉庫運営に悩みをもつあなたに、自信をもって本書をお勧めします。
目次
第1部 港湾倉庫(保税蔵置所)の基本情報
第1章 港湾倉庫(保税蔵置所)の役割
1. 港湾倉庫(保税蔵置所)と輸出入貨物
2. 在来船と港湾倉庫(保税蔵……
わかりやすい材料学の基礎
菱田博俊 著
【はじめに】
●本書の目的
この本は、大学の教養過程において理工系の学生が材料の基礎について初めて学習するにあたり、できるだけ抵抗なく、取っ掛かりとしての広範囲の知識を得られる様にと企画構想した、言わば初心者用の「材料学」の教科書である。工学で用いられている材料全般を視野に、特徴を比較しながら、初めて材料を学ぶ際に先ずは知ってもらいたい内容を記載した。将来、こんな場面でこんな物を作りたいのだが、その時にこの様な材料をこの様な感じで使えば良いだろうか、と漠然とで結構なのでイメージを持てる様になってもらえれば嬉しい限りである。
その意味、……
船体運動 操縦性能編(改訂版) 船舶海洋工学シリーズ3
安川宏紀 芳村康男 共著
「真っ直ぐ走る」、「曲がる」、「止まる」に代表される操縦性能は、一般に、平水中を航行する船の操舵ならびにプロペラの操作に対する運動応答性能を指します。
本書は、加減速を伴う直進運動、プロペラ逆転停止運動、針路変更時の運動、大舵角時の旋回運動、zig-zag運動、港での離着桟運動等の操縦運動について、できるだけ統一的に理解できるように整理しています。
【まえがき】より
本書は、船の操縦運動について述べたものである。船の操縦運動についての知識は、船の運航者や設計者にとって不可欠である。
船の運動性能は、耐航性能(seakeep……
造船工作法 船舶海洋工学シリーズ9
奥本泰久・大沢直樹・青山和浩・後藤浩二・尾田 逸人・田崎泰博・津川博光・中山祐蔵・野口千年、濱田雄二 共著
造船工作の全体的流れ、工作・造船の要素技術、各種の工場設備、生産管理の概要と工程計画・管理の技法、造船における品質管理について説明。さらに、進水工作法、安全衛生、現図について詳説。
若手造船技術者の自習教材、船舶工学を学ぶ学生に最適のテキスト。
【まえがき】より
造船は、鋼板構造の部品切断・接合・組立て・ブロックの搭載、ならびに部品・機器・装置等の配置・据付けを行う総合組立産業である。1975?1977年に日本造船学会鋼船工作法研究委員会(以下で「工作法研究委員会」と呼ぶ)が編纂した「新版 鋼船工作法」(以下で「原版」と……
船体運動(耐航性能編) 船舶海洋工学シリーズ4
柏木 正・岩下英嗣 共著
自由表面船舶流体力学の理論は先達の努力によって築き上げられてきた大変「美しい」理論。それに気付き魅了され始めると船舶耐航性理論を理解するのは意外とた易いかもしれません。
本書は、波浪中での船体運動理論をこれから学ぼうとする大学生や大学院生、あるいは船舶海洋関連企業で船舶や浮体の波浪中性能の仕事に携わる人たちを対象として、必要な知識や理論をまとめたテキストです。
【まえがき】より
船の運動性能は、波浪中での耐航性能と平水中での操縦性能に大別されますが、本書は耐航性能について書かれており、波浪中での船体運動理論をこれから学ぼ……