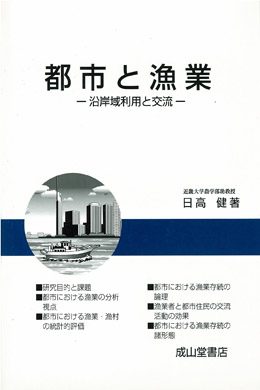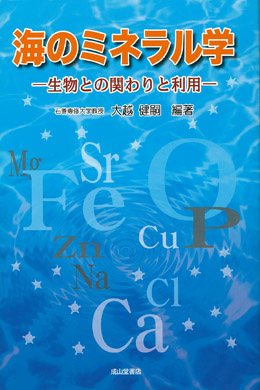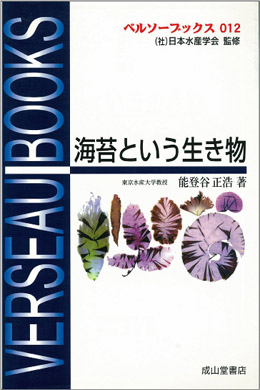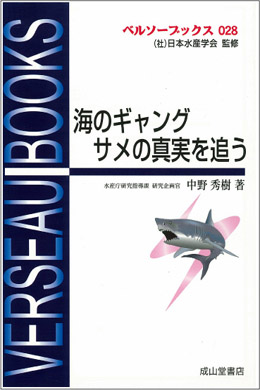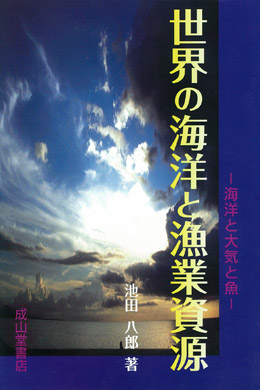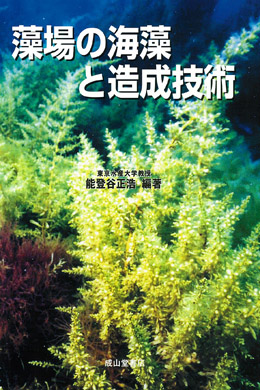水産の書籍紹介
最新のサケ学 ベルソーブックス011
帰山雅秀 著
サケとマスはどう違うのか。サケはどうして故郷の川へ帰ってくるのか。サケの小型化・高齢化現象とは何か。
サケによって維持される自然環境とは。「海からの贈り物」サケの不思議と魅力のすべて。
【はじめに】
日本人とサケは、古くは縄文時代から深いつながりを持ってきたと言われている。サケが生まれた川に帰ってくることは江戸時代の『和漢三才図会』(1712年)という書物にみることができる。このようになじみみの深いサケであるのに、どういうわけかその生物学に関しては、これまで十分な内容を記載されたものがなかった。
サケはどうして故郷の川に帰ってくるの……
魚のウロコのはなし ベルソーブックス027
吉冨友恭 著
ウロコを調べる!食べる!利用する!薄いウロコだって、奥が深い。一読すれば思わず目から鱗の、
今までにない「ウロコの専門書」がついに完成!
【はじめに】より
「鱗」と聞くと、みなさんは何を想像するだろう。魚の料理で鱗を取るのに苦労したこと、魚を食べて歯の隙間に鱗が挟まったこと、他にも、鯉のぼりの模様を思い浮かべる人もいるのでは・・・。筆者には魚屋の大きなまな板や床についた鱗が洗い流されていく光景が目に浮かぶ。幼少の頃に親しんだ大阪の黒門市場で毎日のように見ていたせいかもしれない。
鱗は多くの人にとって身近なもののはず。水産大……
捕鯨に生きた
大洋漁業南氷洋捕鯨船団の記録を残す会 編
日本のあらゆる産業を支えてきた捕鯨事業。その従事者たちがダイナミックな体験談、公海商業捕鯨再開への希望を思い思いに綴る。
【目次】
1:捕鯨三隻,氷山に閉じ込められる
2:遭難捕鯨船救出作戦に成功
3:抹香フライキ(旗)
4:三代社長に仕えて
5:南鯨戦後第一回の出漁
6:私の捕鯨人生
7:捕鯨船事始め
8:若き日の失敗談
9:航海実習生
10:南氷洋捕鯨の電波利用物語
11:一五回出漁の軌跡
12:今,甦る鯨の世界
13:ソロモン海で第二日新丸炎上!
14:南氷洋の気象雑感
15:山家男のくじらとり
16:第二〇次南鯨便り
17:……
都市と漁業−沿岸域利用と交流−
海のミネラル学−生物との関わりと利用−
大越健嗣 編著
本書は、海水や海洋生物に含まれるミネラルに着目し、生物とどのような関わりがあるのか、またミネラルを利用してわかることは何か、などについてわかりやすく解説しています。冒頭の海洋深層水やタラソテラピー以外にも、ミネラルを利用したウナギやアユの回遊履歴の解明やカキの産地判別への応用、特定のミネラルを多く蓄積する生物などに関する記述もあります。ミネラルと聞くと一般的にはどうしても健康と関連付けてしまいたくなりますが、そればかりではなく、様々な分野での利用可能性を示しています。
これまで海のミネラルに関する本は、それぞれの立場から断片的に書……
水産・海洋ライブラリ6 水産物の利用 ー原料から加工・調理までー【2訂版】
山中英明・田中宗彦 共著
鮮度低下の速い魚類・軟体類・甲殻類など魚介類の原料特性と調理法、缶詰・調味加工品への加工法をわかりやすく解説する。
【目次】
第1章 水産物統計
1.1 世界の主要国別漁業・養殖業生産量
1.2 日本の漁業・養殖業生産量及び生産額
1.3 水産物の輸入
1.4 主要水産加工品の生産量
1.5 日本人1人1日当たりの動物性タンパク質供給量
第2章 水産加工の目的と魚介類の原料特性
2.1 水産加工の目的
2.2 魚介類の加工原料としての特性
2.2.1 漁獲量の不安定性
2.2.2 原料の多種多様性
2.……
海苔という生き物 ベルソーブックス012
海のギャング サメの真実を追う ベルソーブックス028
中野秀樹 著
凶暴なものや温和なもの。大きいものや小さいもの。資源豊かなものや絶滅に瀕するもの。“サメ”とはいったい、
どんな生き物なのだろうか?それぞれが持つ魅力と、人とサメの共存への道を探る。
【目次】
第1章 サメの生態
1-1 サメは何種類くらいいるのか?
1-2 サメは軟骨魚類である
1-3 サメはどのように増えるのか?
1-4 サメはどこに棲んでいるのか?
1-5 サメの体と感覚器官
1-6 サメはなにを食べているのか?
第2章 サメの利用
2-1 人間はどのようにサメを利用してきたのか
2-2 サメ料理
2-3 ……
世界の海洋と漁業資源−海洋と大気と魚−
藻場の海藻と造成技術
能登谷正浩 編著
藻場は、魚介類のゆりかごとして、また沿岸の環境を保全する上で、きわめて重要な役割を果たしています。しかしながら、高度経済成長期から現代にかけて埋立て等による沿岸開発が進められた結果、数多くの藻場が消失してしまいました。現在全国各地で“藻場再生プロジェクト”が進行しているが、思うような成果が上がらない場合も多い。
本書は「藻場の造成は真に科学的、生物学的な認識や十分な根拠を基礎として行われるべきである」として、藻場を構成する海藻の生物特性とそれを造成技術にどのように応用すべきかを示したものです。
内容は、ホンダワラ類、コンブ類、ア……