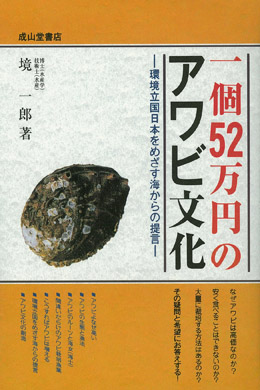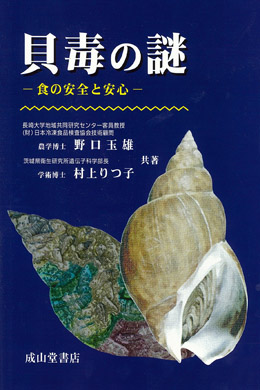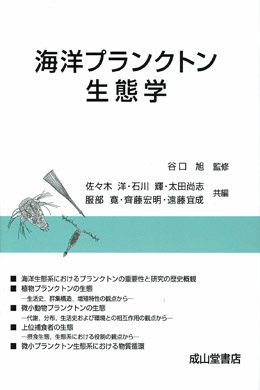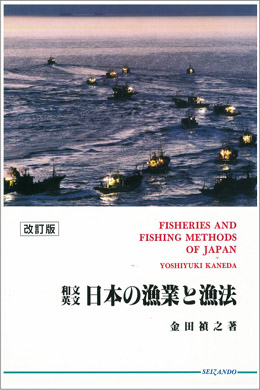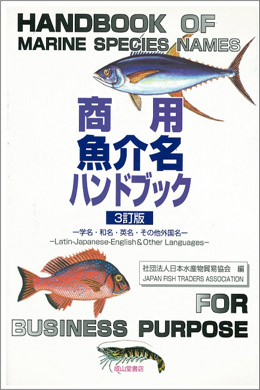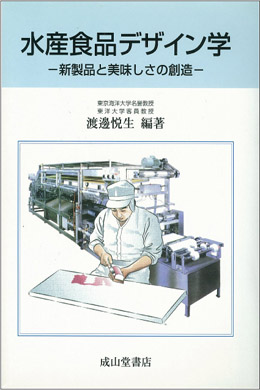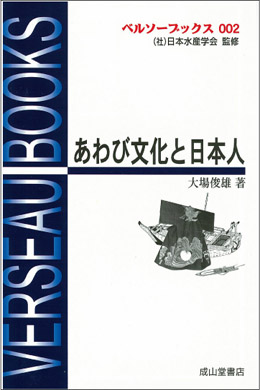水産の書籍紹介
日本漁具・漁法図説 【四訂版】
金田禎之 著
467種の代表的な漁業を選び、漁具・漁法を機能的かつ厳密に定義し体系的に分類。漁具・漁法・漁期・漁獲物・漁場について図説。
【序文】より
日本の漁具・漁法は、多種多様の魚介類を対象として漁民が長い歴史の過程で工夫し改良を加えてきた産物であり、零細・単純のものから大規模・複雑巧緻を極めたものまですこぶる変化に富んでいる。戦後は更に、編地に化繊を、又、浮子に合成樹脂製品を使うというように、その素材が大きく改良されるとともに、漁具・漁法の様相は昔日の面影を一新した感が深い。
明治43年に出版された「日本水産補採誌」は、……
一個52万円のアワビ文化−環境立国日本をめざす海からの提言−
境 一郎 著
世界一の高級食品アワビを安く大量に作る方法は? アワビとコンブの複合養殖を提唱し、漁場の再生と日本独特のアワビ文化を解説する。
○アワビと日本人の深い絆を探り、
○磯焼けで荒れ果てた海、ヘドロで埋まった湾を再生し、
○アワビが一般の人にも気軽に食べられるようになり、
○二酸化炭素を減らして地球温暖化防止にも役立つ!
こんなおいしい話が盛りだくさんの本です!
【目次】
第一章 アワビよなぜ高い
1.アワビ一個52万円
2.アワビ食べれば死刑!の江戸時代
3.秦の始皇帝と不老長寿の薬
4.値段は水産物のチャンピオン
5……
貝毒の謎−食の安全と安心−
野口玉雄・村上りつ子 共著
新鮮な貝が麻痺や下痢等の毒をもつのはなぜか、その毒化の仕組から中毒症状、予防措置までを丁寧に解説。全ての食品衛生関係者必読の書。
【目次】
第1章 麻痺(まひ)性貝毒
1 麻痺性貝毒とはなにか
2 麻痺性貝毒を作るプランクトン
3 毒化する生物たち
4 毒の蓄積部位
5 魚類などの被害
6 麻痺性貝毒の化学
7 世界各地の麻痺性貝毒による汚染と中毒状況
8 貝の毒化を予防する
9 毒化した貝は利用できるか
10 国際間のトラブル
第2章 記憶喪失性貝毒(ドウモイ酸)
1 記憶喪失性貝毒とはなにか
2 記……
海洋プランクトン生態学
谷口 旭 監修・佐々木洋・石川 輝・太田尚志・服部 寛・齊藤宏明・遠藤宜成 共編
地球上の約7割を占める海には様々な生物が生息し、それぞれが織りなす生命活動によって海洋生態系は成り立っています。
その中でも重要な働きを持つのがプランクトンである。新たなエネルギーを作り出す生産者として、また、食物連鎖の最も下層に位置する被食者としてなど、物質循環の基盤を担っている。その存在なくして海洋生態系は成り立たちません。
本書は、プランクトンと多岐にわたる生物のエネルギー伝達経路に重きを置き、研究の歴史から種類、生活史、生物存続の戦略、物質循環における役割などが解説されています。
海洋生態系の様々な側面を捉えた本書は、生物海洋……
カツオの産業と文化 ベルソーブックス018
若林良和 著
初ガツオ、カツオのタタキ、かつお節と食卓でおなじみの魚、カツオ。でも食べるだけじゃ物足りない!
生態から一本釣りの現場、かつお節の製造法、地域おこしまで、カツオと人のつながりを広く紹介。
【はじめに】より
「毎年、買っているのよ。本場のタタキは、やっぱり良いわ」と嬉しそうに、ご年配の女性が声をかけてきた。
「一節1,600円です。ありがとうございました」
カツオのタタキを手渡す水産商工課の女性職員と私。テントの前で別の男性職員と商工会メンバーが息の合ったワラ焼きタタキを実演し、その裏では水産商工課長が自慢の包丁でカツオを……
和文・英文 日本の漁業と漁法 【改訂版】
複雑な日本漁業を漁業制度と漁法の上から分類し豊富な図で解説。重要項目に英文併記。制度・法律の改正に併せた改訂版。
【まえがき】より
日本の漁具と漁法については、1977年に日本各地のものについて、取りまとめて「日本漁具・漁法図説」として刊行して以来、一部改正して「増補改訂版」として現在に至っている。最近、内外からもう少しコンパクトなものを作ってほしいとの要望が多く、これに応えたものが本書である。
日本の漁具・漁法は、日本の漁業の長い歴史の積み重ねによりもたらされたものであって、それは、小規模、零細・単純なものから、大規模、複……
商用魚介名ハンドブック【3訂版】−学名・和名・英名・その他外国名−
(社)日本水産物貿易協会 編
貿易対象魚介類及び海外種・日本近海種1909種の学名・和名・外国名を産地や毒性等の特記事項を加えて収録。主要魚介は口絵にも掲載。
●魚類、甲殻類、軟体類、水棲無脊椎動物類、海藻類のうち、易の対象となる種に加え、
これら海外種を中心に日本近 海種を含め総計1909種を採録。
●全種を28の章に類別、学名・和名・外国名・産地・毒性等の特記事項を記載。
●学名、和名、外国名の3パターンから引ける索引を掲載。
●新たに「魚介類の名称のガイドラインについて(中間とりまとめ)」を追加
【目次】1.ヤツメウナギ、サメ類2. ……
水産食品デザイン学−新製品と美味しさの創造−
渡邊悦生 編著
カニ棒のような付加価値の高い商品開発や原料を無駄なく利用するための食品加工技術を、伝統食品の知恵から最新の研究まで具体的に解説。
【はしがき】より
本書は3部から構成されております。第1部「魚をデザインする」では、例えば、これまでそのまずさから好まれなかったスケトウダラやクロカジキをいかに食べられるようにしたか、一度にプール一杯分位に獲れたイワシをどう処理するか、魚の油からどうやってマーガリンを作るかなどなどを平易な文章で面白楽しく紹介しております。
第2部「魚の美味しさの追求」では、例えばピチットシートを用いたアジ開き干しの製造……
養殖マグロビジネスの経済分析−フードシステム論によるアプローチ−
小野征一郎 編著
近年急速に市場を拡大した養殖マグロの生産から流通、消費までを解説。養殖ビジネスの実態を分析する。マグロ関係者必携の一冊。
【はしがき】より
本書は、21世紀COEプログラムに採択された「クロマグロ等の魚類養殖産業支援型研究拠点」の流通・経済部門の成果である。研究の出発点が「クロマグロの完全養殖」にあることは言うまでもないが、流通・経済部門が研究に取りかかった2003年度においては、私を含め研究スタッフの全員が、養殖マグロの日本の主産地が奄美大島であることくらいしか知らなかったと思う。もっともこの事態は今もあまり変わっていないのではな……
あわび文化と日本人 ベルソーブックス002
大場俊雄 著
あわびは、古くから日本人の生活と共にありました。縄文時代には交易品として、奈良・平安時代には貢物として、戦国時代は武将の出陣の儀式に使われるなど、時代によって様々な役割を果たしてきました。
本書は、そんな日本のあわび文化を詳しく紹介。あわびの生態から歴史、食文化、漁業などに至るまで幅広く取り扱っています。
これを読めば、「あわび」のすべてがわかります!
「はじめに」より
荒海の磯に付いているアワビをはがしとると、殻からあふれ出るように盛り上がった身を生きいきとくねらせる。アワビは貝類の中でとび抜けて肉量が多く、しかも食べ……