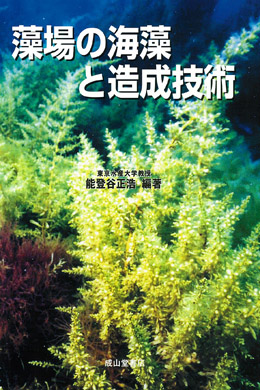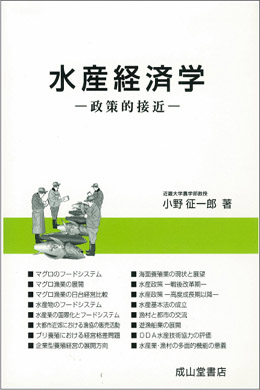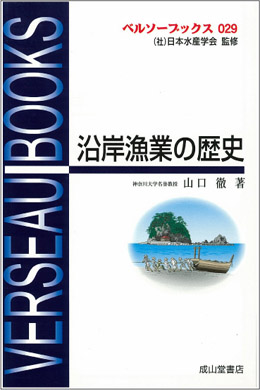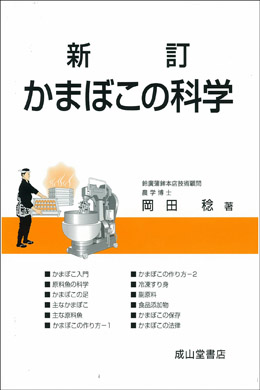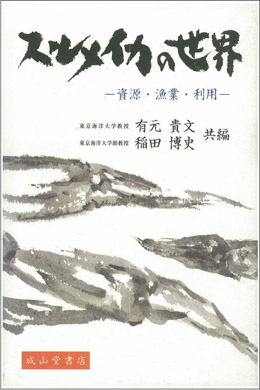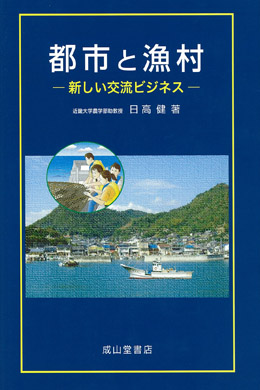水産の書籍紹介
藻場の海藻と造成技術
能登谷正浩 編著
藻場は、魚介類のゆりかごとして、また沿岸の環境を保全する上で、きわめて重要な役割を果たしています。しかしながら、高度経済成長期から現代にかけて埋立て等による沿岸開発が進められた結果、数多くの藻場が消失してしまいました。現在全国各地で“藻場再生プロジェクト”が進行しているが、思うような成果が上がらない場合も多い。
本書は「藻場の造成は真に科学的、生物学的な認識や十分な根拠を基礎として行われるべきである」として、藻場を構成する海藻の生物特性とそれを造成技術にどのように応用すべきかを示したものです。
内容は、ホンダワラ類、コンブ類、ア……
水産経済学−政策的接近−
小野征一郎 著
欧米での健康志向の高まりや中国における魚消費量の増加などから今後は世界的に水産物の価値が高まると予測されています。
そうした中、豊かな漁場環境に恵まれ、世界有数の水産大国である日本の水産業も単なる食糧生産産業の枠を超え、海そのものの利用、保全をも包括した新たな産業としての発展が政策課題となっています。
本書は、水産政策審議会会長として、そうした水産政策の審議に長年携わってきた著者のこれまでの研究の集大成となっています。 最近注目のマグロ漁業の話題にはじまり、養殖業、水産物流通、水産基本法の検討、さらには近年注目されている漁村活性化や……
水産・海洋ライブラリ7 海の集団生物学
渡邊精一 著
カニ博士による水産資源管理のための生物学の入門書。生物の生活史、群集の構造、病気の伝播、遺伝などを通して管理のイメージを学ぶ。
【目次】
第1章 水産生物の生活史(life history)カニを中心に
1-1 ズワイガニの生活史(深海で生活するカニ)
1-2 ガザミの生活史(浅い海で生活するカニ)
1-3 ショウジンガニの生活史(海で生活するカニ)
1-4 モクズガニの生活史(河川と海で生活するカニ)
1-5 サワガニの生活史(陸水で生活するカニ)
1-6 クリスマスアカガニの生活史(森に住むカニ)
第2章 個体の……
魚貝類とアレルギー(改訂版) ベルソーブックス013
塩見一雄 著
世界で一番の魚好き、エビ・カニ好きの日本人。実は世界一の魚貝類のアレルギー大国だった!? 現代人に急増している食物アレルギーとは何か。水産物をメインにその原因と実状を解説し、対応策を探る。
【はじめに】より
日本人の3人に1人は、何らかのアレルギーをもつと言われている。私自身も、数年前に突然花粉症にかかり、毎年2〜4月は鼻水、鼻づまり、くしゃみなどに苦しんでいる。また、大掃除では必ずくしゃみや眼の痛み、呼吸困難などが起こるので、ハウスダスト・アレルギーに、さらに研究で実験動物に用いることから、ウサギ・アレルギーにもなっている……
沿岸漁業の歴史 ベルソーブックス029
山口 徹 著
房総、三浦、瀬戸内など、沿岸で暮らす人々はどのような漁業を営んできたのだろうか。
自然の中で様々な技術をあみ出してきた漁民たち。彼らの生活を振り返り、漁業の変遷を辿る。
【はじめに】より
私が漁業と漁村の歴史に関心を持つようになったのは、それほど古いことではない。つい20年ほど前、わが国の漁業史研究に先駆的な役割を果たしてきた渋沢敬三が創立した日本常民文化研究所の再建に携わってからのことである。その研究を継承するために、まずは漁業・漁村を知ろうと思い、調査に入ったのが千葉県の房総半島や九十九里浜の漁村であり、かつお一本釣りで……
新訂 かまぼこの科学
岡田 稔 著
日本の伝統食品として親しまれてきたかまぼこ。その歴史は古く、300年前の元禄時代には、板つきのかまぼこが料理の一品として作られていたといいます。干物や塩魚などと違って、魚を保存するためではなく,魚を美味しく食べるための手段として始まったかまぼこは、昨今では海外においてもsurimiとして愛好されており、国際的な食品にもなっています。その製造技術は一見シンプルに見えながらも、実に複雑かつ奥深いものがあります。
本書は、かまぼこ発達の流れ、種類、おもな生産地、栄養価などの基礎知識を紹介するとともに、原料魚や冷凍すり身、かまぼこの足、副原……
スルメイカの世界−資源・漁業・利用−
有元貴文・稲田博史 共編
スルメイカ類の生態から生産システム、流通・加工に至るまでを詳説。資源管理を必要とするイカ釣り漁業の国際化に対応するための1冊。 競争から協調へイカ釣り漁業の国際化に対応するための1冊!
【発刊にあたってより】
イカ釣り漁業の国際化に対応するために、過去の漁業展開の歴史を振り返り、次の展開を見通していくことが必要であるとの観点から、平成10年秋「イカ漁業の現状と将来展望」と題したシンポジウムを日本水産学会が主催し、スルメイカ類(アカイカ科)を主対象とした各分野の情報提供がなされました。
これと連動して、漁業懇話会が「国際化時代のイカ……
都市と漁村−新しい交流ビジネス−
日高 健 著
「漁村へのIターンを考えている人」、「観光客誘致の参考書」
に是非読んでもらいたい内容です。
朝市や体験漁業、ダイビング事業など成功例を基に、価値あるビジネススタイルを探る。多様化する漁村の役割を分析し、活性化を目指す!
著者からこの本を読まれる方へ(「はじめに」より)
国民にとって、水産物は重要な食料である。また、豊かな自然に恵まれた海辺は、重要な生活空間である。これらに深く関わりを持つのが漁民であり、漁村である。この漁村が、近年、漁業資源の減少、漁業経営の悪化、漁業者の減少と高齢化などによって、非常に厳しい状態に追い込まれている……
水産・海洋ライブラリ8 海洋生産機械概論
海藻の食文化 ベルソーブックス014
今田節子 著
健康食として注目されている海藻。日本では古くから薬効をもつ食べ物として、今よりも多種類の海藻が利用されていた。
海藻の食文化を見直すことで、新しい利用法も見えてくる!
【目次】
第1章 海藻とは何か?海藻の食文化を理解するために?
1-1 海藻と海草はどう違う
(1)海藻と海草を区別する
(2)海草利用の伝統
1-2 海藻の分類と特徴
(1)色による海藻の分類
(2)「〜モ」「〜メ」「〜ノリ」
1-3 海藻が生える環境とその採り方
第2章 食用海藻の種類と移り変わり
2-1 食べている海藻は一握り
2-2 昔はた……