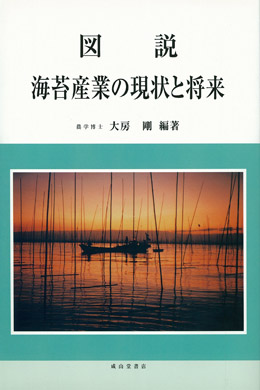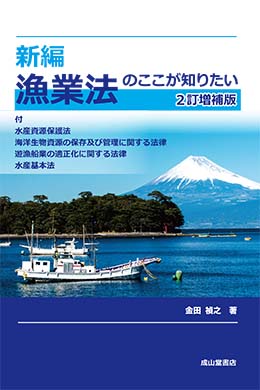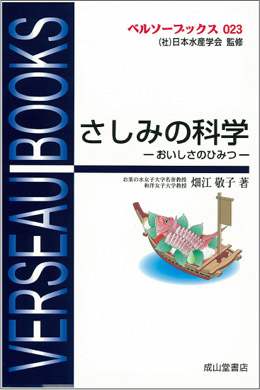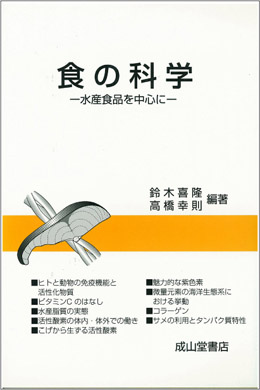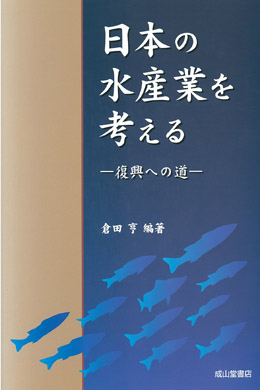水産の書籍紹介
図説 海苔産業の現状と将来
大房 剛 編著
大きな転機を迎えている海苔産業を豊富な資料・写真で詳しく解説。将来の活路を見い出す1冊。データブックとしても最適。
【目次】
第1章 日本での水産業の推移
1.1 水産業生産金額合計の推移
1.2 漁業部門別生産金額の推移
1.2.1 遠洋漁業での推移
1.2.2 沖合漁業での推移
1.2.3 沿岸漁業での推移
1.2.4 海面養殖業での推移
1.2.5 年度ごとの合計金額を100とした漁業部門別比率の推移
1.2.6 1970年の生産金額を100とした比率の推移
1.3 海面養殖業での種類別金額の推移
1.3.1 ……
海藻フコイダンの科学
山田信夫 著
本書は、フコイダンとはどのような物質であるのか。また、どのような医薬効果があるのかを多くの図表を用いてわかりやすく解説したものです。化学構造・理化学的性状などを解説した上で、抗がん作用・血栓予防効果・血圧低下作用などの医薬効果や皮膚老化予防などの美容効果等の作用機序を解説する構成となっています。また、人間に対する効果ばかりでなく、養殖魚介類の生態防御活性の増強に関する記述も記載されています。
これまで、フコイダンに関する様々な研究論文が発表され、またテレビなどの情報番組などでも、フコイダンに関する情報が断片的に取り上げられることも……
新編 漁業法のここが知りたい【2訂増補版】
金田禎之 著
漁業法は漁業生産に関する基本制度を定めた法律であり、水産資源の保護培養を目的とした水産資源保護法と不可分一体として運用されています。法の適用対象は広範にわたっており、漁業関係者をはじめ、海運業、遊漁船業等の事業者や、釣り人、サーファー、ダイバーなど、多くの人々と関わりがあります。
このため、法に対する理解の不十分から、トラブルが生じたり、漁業と他分野との利害対立から争いが生じたりすることも少なくありません。埋立てなどによる漁業補償の問題も、本来漁業法は補償とは無関係な法律でありますが、漁業権との絡みもあって誤解されやすいです(実……
音で海を見る ベルソーブックス007
古澤昌彦 著
【はじめに】より
日本人は、魚を好物としている。魚を多く食べるから寿命が長いといわれる。しかし、魚を食べるときに、この魚はどこで生まれ、どのように育ち、どのように獲られ、どのようにここまで運ばれたか、と聞かれても、私を含めほとんどの人が答えられないだろう。大根などは、日頃畑などを目にしているので、およその見当がつく。このように、私たちは、魚から非常な恩恵を受けている割には、その知識に乏しい。これはやはり、魚は、海中という私たちには簡単に見えないところで生まれ育つためである。
海の中は陸上と違って、電波はほとんど伝搬できず、音波の方がず……
さしみの科学−おいしさのひみつ− ベルソーブックス023
畑江敬子 著
「さしみ」や「すし」はなぜおいしい?
旬のテクスチャーなど、ナマの魚介類には欠かせない、
おいしさのひみつを科学的に解明する。
【はじめに】より
初めて訪れた土地の食品市場やスーパーマーケットへ行くと、ワクワクする。日本国内でも外国でも同じである。旅行の楽しみは人によってそれぞれと思うが、どうやらこれは私だけではないらしい。
私は調理学を専門にしているので、同じ仲間と外国へ旅行すると、必ずそこのスーパーマーケットへ行く。その地域の人々が、どんなものを食べているか興味津々なのである。外国へ旅行するチャンスがそんなにあるわけではないが、……
マグロの科学−その生産から消費まで−
小野征一郎 編著
マグロに関する定番書「マグロの生産から消費まで」に、マグロの完全養殖や最新の市場動向など大改訂をもり込み改題。
【目次】
第1章 マグロの種類と生態
第2章 マグロ類の増養殖の現状と将来
第3章 マグロ漁場の海洋環境
第4章 マグロ漁業資源とその漁具・漁法
第5章 マグロ漁業の展開と日かつ連の活動−「98年減船」以降−
第6章 マグロ肉の特性
第7章 マグロの利用・加工
第8章 マグロの冷蔵・冷凍技術
第9章 マグロの需給関係と市場構造……
食の科学−水産食品を中心に−
鈴木喜隆・高橋幸則 編著
我々の健康に深くかかわる免疫活性化物質・必須微量元素・コラーゲン・ビタミンC・活性酸素の特徴・働き等を水産食品中心に解説。
【目次】
1 ヒトと動物の免疫機能と活性化物質
1-1 はじめに
1-2 ヒトと哺乳動物の免疫機構
1-3 魚類とエビ類の免疫機構
1-4 免疫活性化物質とは何か
1-5 免疫活性化物質の種類と作用
1-6 免疫活性化物質の正しい摂取法 2 ビタミンCのはなし
2-1 はじめに
2-2 古代から恐れられていた壊血病
2-3 アスコルビン酸化
2-4 ビタミンCの生理作用
2-5 ビタミンC……
日本の水産業を考える−復興への道−
倉田 亨 編著
近年、世界的に水産物の価値が見直される中で、日本の漁業は漁獲量の減少、担い手不足による高齢化、漁村地域の活力低下により衰退を余儀なくされています。水産物自給率が5割を下回り、水産業の立て直しが急務となるいま、水産業は転換期をむかえ、大きく変貌しようとしています。
本書はそうした中、漁業経済研究における各分野の第一人者が「日本水産業の復興」をテーマにそれぞれの専門分野から持論を展開しています。
内容は、資源管理、漁業経営、市場・流通問題、漁村の活性化、諸外国との関係等と多岐にわたっており、その主張には頷かされる点も多くあります。日本の水……
水産・海洋ライブラリ1 漁業情報学概論
小倉通男・竹内正一 共著
水産分野でも数々の最先端技術の導入が進んでいる。本書は、最新の漁業情報の現状と利用について学校向け教科参考書としてまとめたもの。
【目次】
第1章 漁業情報
1.1 漁況と海況
1.2 漁業情報とその種類
1.3 漁海況の予測と予報
第2章 漁海況情報事業
2.1 漁海況予報事業の沿革
2.2 漁海況情報事業の現況
2.2.1 漁海況情報作成業務
2.2.2 漁海況情報サービス業務
2.2.3 人工衛星利用水産海洋情報
2.2.4 水産物市場情報
第3章 多獲性魚類の漁況
3.1 イワシ類
3……
貝殻・貝の歯・ゴカイの歯 ベルソーブックス008
大越健嗣 著
貝殻は身を守るためにある?。歯はものを噛むためにある?。ホントにそれだけ?貝殻や貝の歯に秘められた様々な役割、ふしぎな現象、有効利用法に目を向けてみよう!
【はじめに】
ちょっと乱暴な言い方だが、生物の体は硬い部分と軟らかい部分でできている。ウイルスなどのきわめて微小な生物を除いて、骨や歯、貝殻、甲羅(甲殻)、サンゴなど、ほとんどの生物は何か硬いものを体のどこかにもっている。それなのに一般の関心は軟らかい部分にかたよっているし、軟らかい部分を研究している人の数もはるかに多い。
たしかに、DNA、RNA、タンパク質、糖、脂質といった軟……