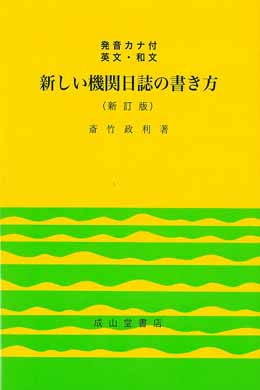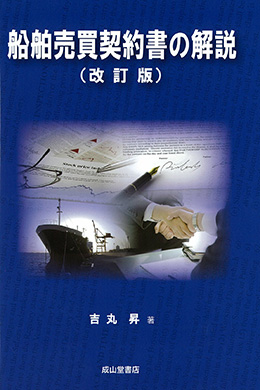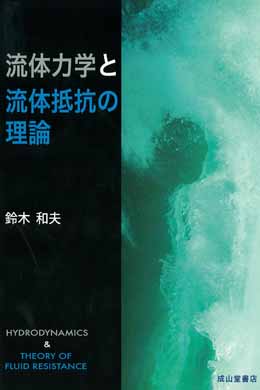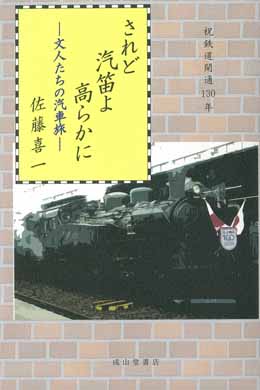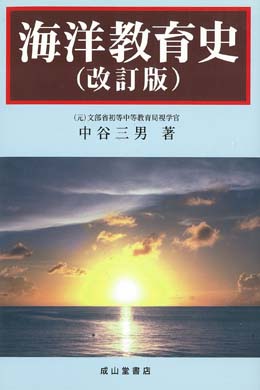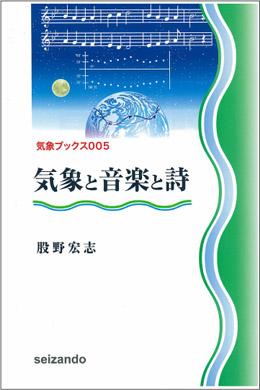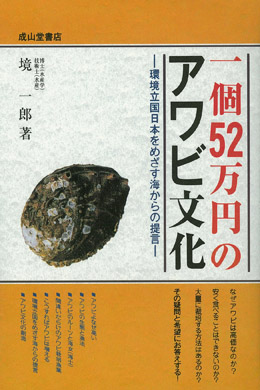成山堂書店の書籍紹介
発音カナ付英文・和文新しい機関日誌の書き方【新訂版】
斎竹政利 著
最もわかりやすい英文機関日誌の書き方。基礎となる語句や英文の書き方、話し方を紹介。事故・緊急時の文例も豊富に収録。船舶機関士向。
【目次】第1編 機関日誌 第1章 機関日誌の種類 第2章 機関日誌の取扱いと記載上の心得 第3章 機関日誌
第2編 基礎 第1章 始めに知っておきたいこと 1.発音について 2.語の配列順序 3.英文における習慣 4.八品詞 第2章 奇数と序数 第3章 日づけ 第4章 時刻 1.時刻の書き方 2.時刻変更の必要と日付変更線 3.時刻の変更 第5章 天候・波浪(海上の模様)・風力……
船舶売買契約書の解説(改訂版)
吉丸 昇 著
「船舶売買契約」のバイブル!
基礎知識、トラブル防止策など契約上のノウハウを満載。
「これだけは、知っておきたい」という情報が詳説されている、関連業務に携わる方、担当部署には、必携の本です。
船舶売買契約の基礎知識と取引の過程で予測されるトラブルの防止策など、契約上のノウハウを詳説。契約の条文にそって問題を掘り下げながら、「例題」も交えてわかりやすく逐条解説する。
今回の改訂版では、昨今の船舶売買に関する国際ルースの改定について、新たに公表された「SALEFORM2012」の主旨を踏まえながら「NIPPONSALE1999……
航海計器シリーズ2 ジャイロコンパスとオートパイロット【新訂増補】
前畑幸弥 著
※在庫が少なくなっており、品切れの場合がございますのでご了承ください。
最新の資料に基づき、原理、構造、作動などについてわかりやすく説明。特に適応オートパイロットについて1章をさいて説明。
【新訂増補に当たって】より
最近、マイクロプロセッサの発達につれて、適応オートパイロットが実用化されました。このオートパイロットは、自船の操縦性や外部環境の変化に適応するよう、各種調整が自動的に変化、調整されます。したがって単にディジタル化されているだけでなく、これと同時に適応化されており、省エネルギー操舵に役立つことが認識され、かなり普……
Case Studies : Ship Engine Trouble
NYK LINE Safty & Environmental Management Group
外国人船員にもわかりやすい英語版。双方で持てば、より意志疎通が明確になる。混乗船の機関長必携の機関図書!
(A) Combustion System
Fractured Piston Ring/Cracked PistonCrown/Malfunction of Main Engine due toPoor-Quality FuelOil/Abnormal Abrasion of Cylinder Liners/Exhaust valve Seat CorrosionHole/Malfunction of Exhaust Va……
流体力学と流体抵抗の理論
鈴木和夫 著
水や空気という流体の流れの現象を扱う流体力学、その応用である流体抵抗。この二つを盛り込んだ、初学者も技術者も使えるテキスト。
【まえがき】より
流体力学は水や空気と言う流体の流れの現象、すなわち流体の運動を扱う学問ですが、その重要な使命の1つに、流体機械、自動車、航空機、船舶といった流体に関係する物体に加わる流体を推定し、かつそれらのデザインに応用するということがあげられると思います。本書はそのタイトルに「流体力学と流体抵抗の理論」と銘打っていますように、単に流体力学について紹介するだけではなく、一様な速度で前進している物体……
されど汽笛よ高らかに−文人たちの汽車旅−
佐藤喜一 著
文人たちやその作品に描かれた主人公の汽車旅をたどって現地を訪れ、当時の時刻表や資料によって検証し,往時を偲ぶ鉄道エッセイ。
【目次】
1.伊香保の宿から山科駅の別れまで−蘆花『不如帰』の旅路
2.「嗚呼 山林に自由存す」−独歩〈夢追い人〉の汽車旅
3.停車場に詩情求めて
A 函館本線 ニセコ駅−『生まれ出づる悩み』の一夜
B 上越線 新前橋駅−萩原朔太郎ゆかりの駅
C 平成筑豊鉄道 東犀川三四郎駅−小川三四郎のふるさと
D 「・・・・・・小田急線は我が絹の道」−変わる新宿 あの・・・・・・
4.「・・・・・・うたふがごとき……
海洋教育史 【改訂版】
中谷三男 著
明治から現代に至る各練習船教育機関の生い立ちや入試概況・教育内容・練習船の変遷等を豊富な資料で紹介。大学再編等海事教育界の動向や各校の練習船・実習船の写真をつぶさにとり入れ、一層の充実を図った。
気象と音楽と詩 気象ブックス005
股野宏志 著
ベートーヴェンの「月光」は、低気圧の通過を表現していた!?先人達が音楽・詩歌に託した「気象」を鑑賞し、現代の生活で忘れがちな「自然への素朴な感動」の世界へご招待します。
【まえがき】より
われわれは大気の底に住んでいるので、気象の恩恵と脅威を受けながら毎日の暮らしを営んでいる。しかし、気象の恩恵は、空気の存在を忘れるように、当たり前に事として心に留められることもなく、気象の脅威も、災害は忘れたころにやってくるのたとえの通り、記憶が薄れていく。脅威を代表する暴風雨は天気予報の原点で、特に台風と梅雨期の雨は災害を伴う気象の筆頭とし……
日本漁具・漁法図説 【四訂版】
金田禎之 著
467種の代表的な漁業を選び、漁具・漁法を機能的かつ厳密に定義し体系的に分類。漁具・漁法・漁期・漁獲物・漁場について図説。
【序文】より
日本の漁具・漁法は、多種多様の魚介類を対象として漁民が長い歴史の過程で工夫し改良を加えてきた産物であり、零細・単純のものから大規模・複雑巧緻を極めたものまですこぶる変化に富んでいる。戦後は更に、編地に化繊を、又、浮子に合成樹脂製品を使うというように、その素材が大きく改良されるとともに、漁具・漁法の様相は昔日の面影を一新した感が深い。
明治43年に出版された「日本水産補採誌」は、……
一個52万円のアワビ文化−環境立国日本をめざす海からの提言−
境 一郎 著
世界一の高級食品アワビを安く大量に作る方法は? アワビとコンブの複合養殖を提唱し、漁場の再生と日本独特のアワビ文化を解説する。
○アワビと日本人の深い絆を探り、
○磯焼けで荒れ果てた海、ヘドロで埋まった湾を再生し、
○アワビが一般の人にも気軽に食べられるようになり、
○二酸化炭素を減らして地球温暖化防止にも役立つ!
こんなおいしい話が盛りだくさんの本です!
【目次】
第一章 アワビよなぜ高い
1.アワビ一個52万円
2.アワビ食べれば死刑!の江戸時代
3.秦の始皇帝と不老長寿の薬
4.値段は水産物のチャンピオン
5……