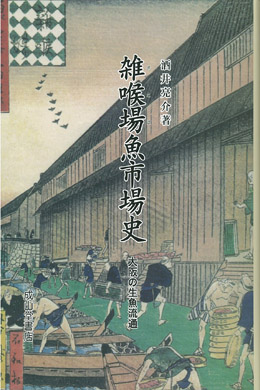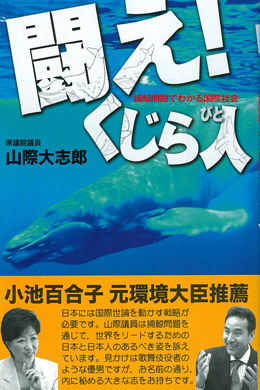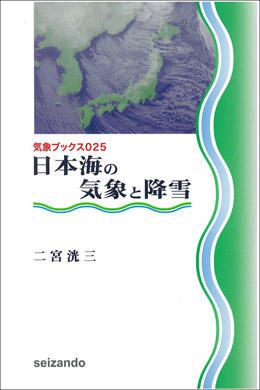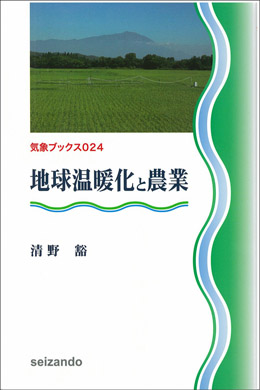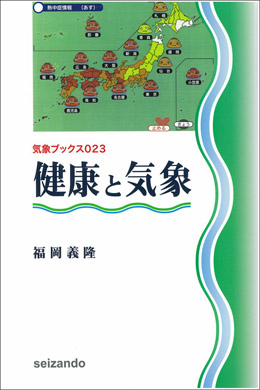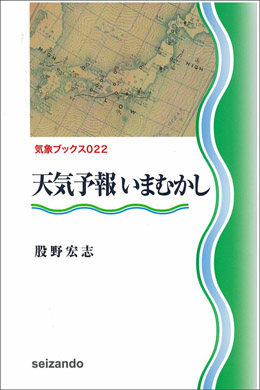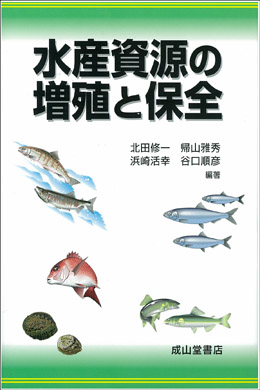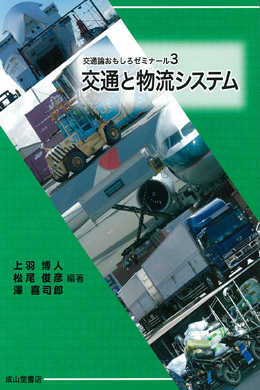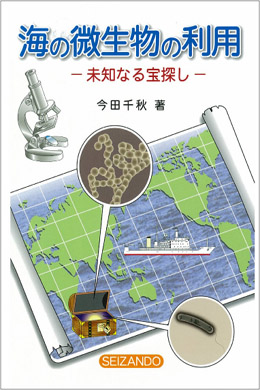成山堂書店の書籍紹介
雑喉場魚市場史−大阪の生魚流通−
酒井亮介 著
「雑魚場」とは一般に魚市場を指す言葉ですが、「雑喉場」といえば大坂の魚市場の通称であり、昭和のはじめに中央卸売市場が開場するまで大阪の魚食文化を支える中心となってきたところです。
「食い倒れの大阪」といわれるように、大阪は古くから独自の食文化を形成してきました。大消費地でありながら好漁場に近く、近世以前から魚を生きたまま市場まで運んでくるなど、おいしく食べるためのさまざまな工夫を重ねてきています。
冷蔵設備もない時代に、危険を冒してどのように生魚を大坂まで運んできたのか。市場で取引はどのように行われてきたか。その魚がどんな値段で……
航空事故の過失理論【改訂版】−如何なるヒューマンエラーに刑事不法があるのか−
池内 宏・海老池 昭夫 共著
【内容】
航空機は本来安全な乗り物ですが,ひとたび事故が起きると多くの人命が奪われる可能性が有り,一般社会に与える影響も多大です。それ故か,近年は過失犯の必罰化の傾向が強まり,機長が訴追されるケースも出てきましたが,これは刑法の原則(謙抑性,最後の手段性)や事故再発防止の観点と必ずしも合致しているとは言い得ません。
本書は,主に民間航空機による航空事故を例に挙げ,一般の交通事故,医療事故,代表的な判例などに照らし合わせ,機長らを中心とした行為者の刑事過失をどこまでに限定するのが妥当といえるのかを考察しています。また,被害者をケアす……
闘え!くじら人−捕鯨問題でわかる国際社会−
山際大志郎 著
欧米諸国はに牛耳られている国際社会、捕鯨問題はまさにそれを映し出す鏡となっている。深刻な食料危機・環境破壊がしせまる今、日本人が新しい世界秩序を構築するカギを握っている!世界が、地球が日本の力を欲している。今こそ出番だ!覚醒よ、日本人!!闘え、くじら人
【目次】
序章 IWCは国際社会の現実を映し出す鏡
第1部 調査捕鯨の正しい知識
第1章 環境保護運動とクジラ
なぜクジラガ環境保護のシンボルなのか
南氷洋サンクチュアリ
環境保護団体の本当の目的は金もうけ/他
第2章 機能停止に陥ったIWCー本当の使命とは
自ら条……
日本海の気象と降雪 気象ブックス025
二宮洸三 著
本書は、元気象庁長官である著者が、これまでの研究・経験をもとに、日本海の降雪という現象を多くの人に理解してもらおうと執筆したものです。
冬季季節風、日本海上の気団変質から雪と人との関わり、気象予報と降雪の関係、温暖化が降雪にもたらす影響まで、日本海の降雪にまつわる全体像がわかりやすくまとめられています。さらに、降雪という現象を理解するために必要な気象学の基礎の説明にも多くのページが割かれており、気象に関する知識を多くの人に広めようという著者の思いが込められています。読み進めることで気象という科学の全体像を理解していくことができるで……
地球温暖化と農業 気象ブックス024
清野 豁
本書は、農水省の研究部門で活躍した農業気象のトップともいえる著者が、地球温暖化のメカニズムや農業へのメリット・デメリット、米・野菜・果物など各種作物への影響など、温暖化と農業の関係を最新のデータに基づきわかりやすく解明しています。そして、世界的に見た飢餓人口問題なども交え50年後、100年後を見据えた予測と今後の適応策を提言しています。
生育や品質、収穫量など、作物によって受ける影響は異なるものの、これだけ状況が変わってくるのかと驚きを感じます。現状を把握し、温暖化を上手に利用し、適応していくことが、今後の農業を支える術となるでし……
健康と気象 気象ブックス023
福岡義隆 著
春に花粉症、夏に熱射病と年間を通して様々な疾患が生活に関係しています。そうはいっても気象と健康医学に関する知識は意外と知られていません。テレビの天気予報で健康を守る対策法を紹介していますが、限られた時間で細かな部分までは伝えられていません。
本書は、そのような健康医学と気象とのかかわりを研究する生気象学について、その第一人者の著者が最新の研究をもって細かく解説したものです。四季を通じた健康歳時記では、季節を代表する疾患が発病する条件や予防法などを記しています。他にも健康と衣食住との関係を歴史を辿りながら述べたり、先人の天候に関する……
天気予報いまむかし 気象ブックス022
股野宏志 著
本書は天気予報の背景にある学問分野の紹介、観測・通信・予報技術の進歩、さらに近年の天気予報の自由化と気象予報士の登場まで、変わり行く天気予報を文化・学問・技術の3つの視点から述べています。
一般向けに天気予報を体系的にまとめたものとして類書はなく貴重な資料といえるでしょう。巻末に天気予報関係の年表が収録されているのもうれしいポイントです。著者は気象庁OBで、数値予報の実現など、長年にわたり予報畑で勤務してきた経験を持っています。
天気予報の歴史書として、気象予報士はもとより、天気予報を利用するすべての人に読んでもらいたい一冊です……
水産資源の増殖と保全
北田修一・帰山雅秀・浜崎活幸・谷口順彦 編著
世界人口の増加にともなう食料、動物タンパクの不足やBSE問題によって、水産物の需要はますます高まりつつあります。しかし、ほとんどの海では水産資源は枯渇・乱獲状況にあり、養殖は環境・化学物質等の生態濃縮のほか飼料という根本的な問題があります。
水産増殖は荒廃した天然資源を補うために、種苗放流を行い、増産を目指すものでシロサケの放流が代表例です。これまでは天然資源に与える影響や、生育する環境、漁獲規制等を真摯に考えてはいなかった増殖事業ですが、本書では、今後は遺伝的に偏る影響や魚が住める限度、人類が破壊した自然環境の修復等を考慮した新……
交通論おもしろゼミナール3 交通と物流システム
上羽博人・松尾俊彦・澤 喜司郎 編著
【内容】
「縁の下の力持ち」といわれる物流は、私たちの生活や企業活動から、日本経済、国際経済をも支えています。たとえばコンビニエンスストアでは、宅配便の発送や受け取りの代行業務があり、その荷物は配送トラックによって運ばれ、またその輸送は、海外から運ばれてくる石油などのエネルギー資源によって成り立っています。これら「物流」が、生活に密着した重要な活動を担っているのです。
本書は、モノの流れを追い、モノの流れの中で用いられている輸送機関(機器)や荷役機器、あるいはそれらを複合したシステムについて紹介し解説したもの。もともと目に見え……
海の微生物の利用−未知なる宝探し−
今田千秋 著
抗癌作用、肌の美白・抗肥満効果等がある有用物質を作る微生物が海に残っている。そのヒントを詰め込んだ本書を読んでいざ宝探しへ!
【目次】
1. 海洋のサンプリング
沿岸のサンプリング
外洋のサンプリング
採水器
採泥器
2. 海洋微生物の分離と培養
海洋細菌と海洋放線菌の分離培地
船上での微生物の分離操作
海洋微生物のコロニー
3. 海洋微生物の特徴
低温微生物
好塩微生物
海水濃度と酵素の生産
海水中に存在する主な元素の組成
耐圧、好圧微生物
4. 海洋細……