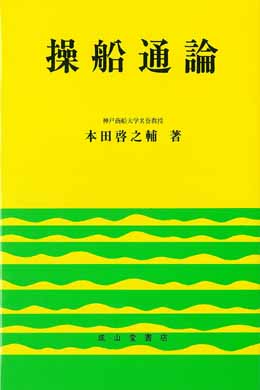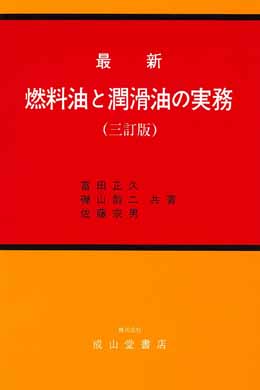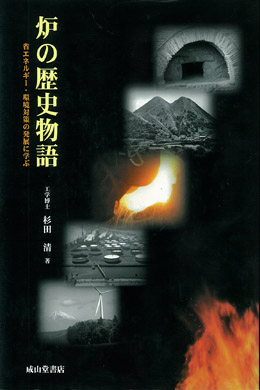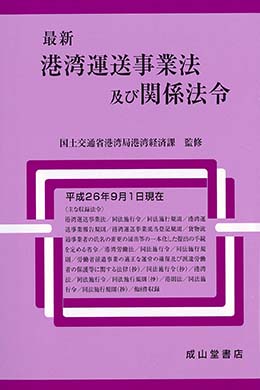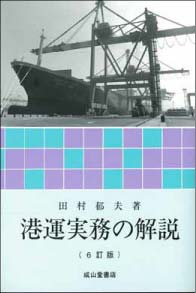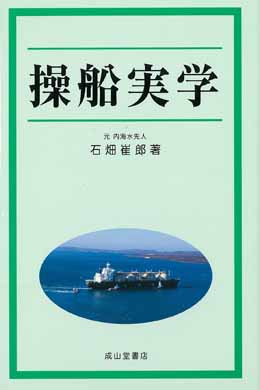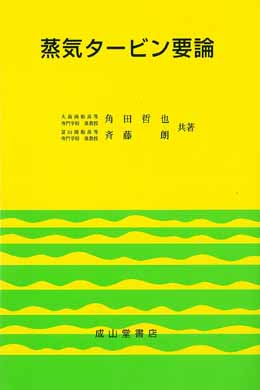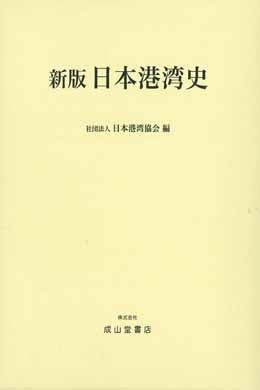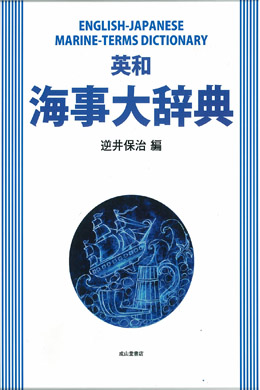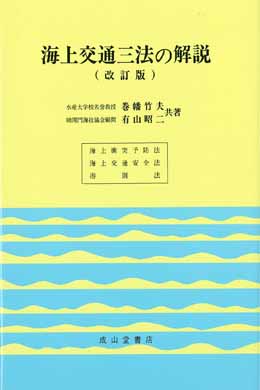海事の書籍紹介
操船通論 【8訂版】
本田啓之輔 著
安全運航に関わる操船性能の基本的知識、錯泊の安全確保、大型船のタグ支援操船を詳細に説明。船長、航海士、水先人、学生必携の書。
【はじめに】より
操船者は船の操縦性能を超えて操縦することはできないし、船の動きの予測を誤ると、ときには大きな海難事故を起こす。このため船の操縦には技量の巧拙が問われるわけで、多くの専門的基礎知識とそれをうまく活用する豊富な海上経験がなければ、判断に的確さを欠き、安全第一の中にも操船の妙味を発揮することはできない。
本書は、操船を操船情報の収集ー思考ー判断ー指示の課程をふむ総合した意思決定……
最新 燃料油と潤滑油の実務 【3訂版】
冨田正久・磯山醇二・佐藤宗雄 共著
燃料油と潤滑油について、石油の成因から製品に至るまでと、その応用技術について最近のデータを採り入れ、体系的にわかりやすく説明。
【まえがき】より
本書の前身である「実用燃料油と潤滑油」が初めて上梓されたのは昭和41年のことで、以来二十数年の経過の間に、世情の激しい変化の中で、幾度かの改訂を行ってきた。さらに、昭和58年には、内容を全面的に見直すと同時に、書名も「燃料油と潤滑油の実務」と改めた。こうしたことにより、多くの読者のご要請に応え得る対応と改革を積み重ねてこられたと確信している。
昭和48年の第一次石油ショック、昭……
炉の歴史物語−省エネルギー・環境対策の発展に学ぶ−
杉田 清 著
人類文明の象徴であり世界産業を支えた「炉」の技術発展と関連する省エネ・環境対策の歴史を時代背景や活躍した人物と共に紹介する。
【まえがき】
われわれ現代人は、直接、間接を問わず「炉」の計り知れぬ恩恵にあずかっている。同時に、そのエネルギー問題や環境対策い悩まされている。文明の象徴であり、人類の生存に不可欠となっている「火」そして「炉」と、どのようにして共生していけばいいのか。これは、21世紀が人類に突きつけている最重要課題の一つである。地球温暖化の問題は、まさにその核心であろう。
その重要性のわりには、炉についての社会全般の関心や……
最新 港湾運送事業法及び関係法令
国土交通省港湾局港湾経済課 監修
港運関係者の業務に必要な法令を収録。平成26年9月に改正・施行された港湾運送事業法・港湾労働法を完全収録。平成26年9月1日現在。
【はしがき】より
四面を海で囲まれた我が国において、港湾は、海上輸送と陸上輸送の結節点として、我が国の産業の国際紛争力を支えるとともに、国民生活の質の向上に貢献するという重要な役割を担ってきました。
近年、経済活動・社会活動のグローバル化がますます進展する中、我が国の産業活動と国民生活を支える港湾も、ハード・ソフト一体となった施策を実施することにより、基幹航路の維持・拡大を図り、国際競争力を……
港運実務の解説 【6訂版】
田村郁夫 著
海陸輸送の結節点である港湾は、物流ターミナルとして、生産と消費を結ぶ流通機構の最も重要な基幹として物流の中核をなすものであり、経済活動にとって大きな役割を担っています。その港湾には、莫大な量の貨物が流動かつ集散していますが、これら貨物の輸送、荷役、荷さばき、保管、包装および情報などを含め貨物の積卸しを主体とする運送にかかわっている港運業務は、意外と複雑で一般には必ずしも理解されておりません。それだけにこれをわかりやすく解説することは容易ではありません。 本書は、港運実務およびこれに関連する分野も含め、できる限り幅広い視点でその業務をと……
操船実学
石畑崔郎 著
四方を海に囲まれた日本では、輸出入の物資の大半が船舶によって運ばれています。船舶はこのような重要な役割を果たしているにもかかわらず、実際の現場でどのように動かされているのかは、あまり知られていません。その船舶の出入港時の操船技術に焦点を当てたものが本書です。海上歴50年余り、現在も瀬戸内海で水先人を務める元船長の労作です。
本書の大きな特徴は、国内外主要港での実経験に基づく多くの操船例を、具体的に記している所にあります。前半部分は船長として経験した世界の海での操船、後半は水先人として携わった瀬戸内海での操船の事例を収録しています……
蒸気タービン要論
角田哲也・斉藤 朗 共著
蒸気タービンは,船舶ではLNG船の主機関や、ディーゼル船におけるターボ発電システムに利用され、陸上では発電所や大工場の電力供給源として採用されています。海上・陸上問わず蒸気タービンには一定の需要があり、これを学ぶための関連書籍も多くありますが、内容が高度であったり、古いなどして、新たに蒸気タービンを学ぶ人に適当なテキストは意外と多くありません。
本書は、蒸気タービンの基礎的かつ重要事項を重点的に取り上げ、初学者でも自学自習できるよう豊富な図を用いてわかりやすく解説しています。蒸気タービンの概要から理論・作動原理・取り扱いに至るまで、……
新版 日本港湾史
(社)日本港湾協会 編
【発刊に寄せて】より
海洋国家である日本にとって、港湾はいつの時代にも国際交流・国際貿易の窓口として、我が国の経済のみならず文化や社会の発展を支える役割を担ってきました。交通通信手段が飛躍的に発展向上した現在においても、我が国の経済を支える輸出入貨物の99.7%が港湾を通して運ばれていることに端的に表されているといえます。こうした今日の港湾の存在と役割は、長い年月にわたる我が国経済経済社会の要請に応え、課題点を一つ一つ克服する幅広い港湾関係者船先達の取り組みによって積み重ねられたものに他なりません。
明治期以降に限ってみても、……
英和 海事大辞典
逆井保冶 編
収録語数約23,000語。帆船時代からの海事全般を網羅し、1000余枚の説明図を付した本格的大辞典。特に帆船用語の充実ぶりは類書を圧倒する。
【まえがき】より
海事用語と簡単に言ってもその範囲は広く、航海・運用・機関・電気・電子・自動制御・造船・海象・気象・法規・保険・運輸・荷役等をはじめとして、他の多くの学問の分野に関連しています。それに加えて古語もあり新語も次々に生まれてまいります。したがって海事用語を統合するには、それぞれの専門分野の多数の学者の協力をまたねばなりませんが、船舶運航者の日常の職務に、船員教育に携わる方々の……
海上交通三法の解説 【改訂版】
巻幡竹夫・有山昭二 共著
海上衝突予防法・海上交通安全法・港則法を逐条的に解説。重要条文の記憶法、理解と確認のための練習問題を収録し、海技国家試験(1〜3級航海)受験者、船長・航海士が海上交通法規を正しくマスター出来るテキスト。
【はしがき】より
この度、海上衝突予防法、海上交通安全法及び港則法の解説書である「明解 航海法規」の新訂版ともいえる「海上交通三法の解説」を執筆いたしました。
本書は、巻幡竹夫先生の労作「明解 航海法規」の明解な解説を基盤とし、その後約10年間の関係法令の改正及び国家試験の傾向の変化に対応するとともに、重要条文、……