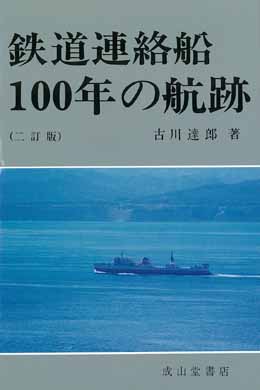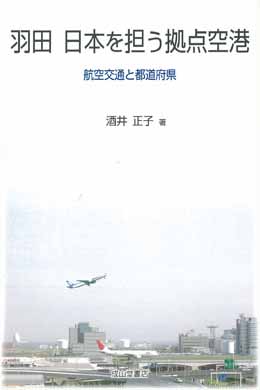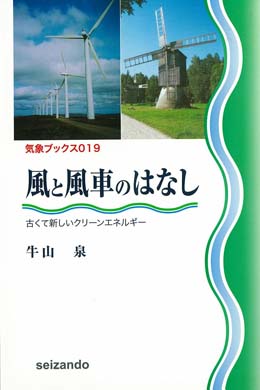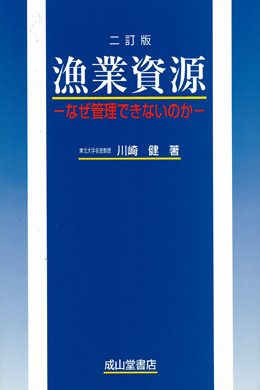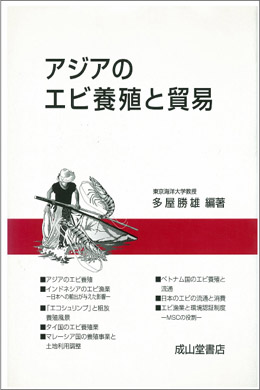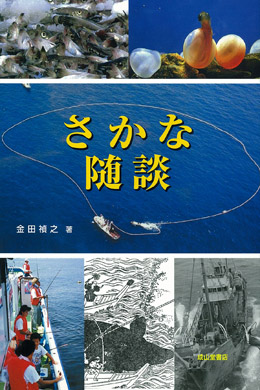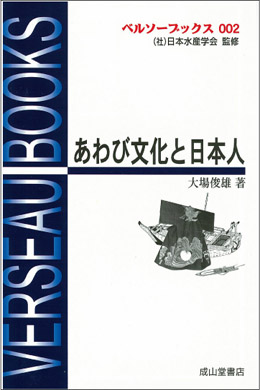成山堂書店の書籍紹介
鉄道連絡船100年の航跡 【2訂版】
古川達郎 著
1世紀にわたって活躍した日本の鉄道連絡船の詳細な記録、各地の連絡船史とテクニカルデータを、建造・艤装に携わった著者の視点で紹介。
第1部 連絡船100年の航跡
第1章 湖ではじまった日本の鉄道連絡船
1.琵琶湖連絡
第2章 川で生まれた連絡船
1.利根川連絡
2.吉野川連絡
3.由良川連絡
4.旭川連絡
第3章 海に出た連絡船
1.徳山−門司−赤間関連絡
2.馬関−門司連絡(関門航路・その1)
3.岡山−高松および尾道−多度津連絡(その1)
4.下関−釜山連絡(関釜航路(その1)
5.大村湾連絡
……
羽田・日本を担う拠点空港−航空交通と都道府県−
酒井正子 著
国内航空の現状を、旅客利便性向上の観点から多頻度運航・ダウンサイジングをキーワードに独自の分析で展望、今後の課題と解決策を提唱する。
【目次】
第1章 わが国の航空輸送市場と世界の航空の動向
1.航空は平和と繁栄が大前提
2.国内航空路線の構造
2.1 旅客需要と運行距離・便数・航空機
2.2 航空機と路線構成
2.3 便数と航空機の関係の経年変化
2.4 事業者の数
2.5 事業者規模と航空機、路線の関係
2.6 運行効率の変遷
3.世界の航空の動向
3.1 航空輸送の実績
3.2 国際機関や……
宇宙と地球環境 気象ブックス002
石田 恵一 著
天文学者が見た地球環境成り立ちの歴史。気象・気候を素材に、地球とは何か、宇宙とは何かを説く。地球の誕生から気象学の確立まで。
【目次】
第一章 気象と気候
一 気候帯
二 大気の循環
三 歴史時代の気候変動
四 縄文時代
五 氷河時代の発見
六 地質時代の気候
第二章 地球の大気
一 二酸化炭素の増加
二 水蒸気が鍵
三 地球温暖化と「事実」
四 生物の発生と資源枯渇
五 酸素と生物
六 まさかより、もしもの備え
第三章 年代測定
一 元素の年齢
二 地球の誕……
風と風車のはなし−古くて新しいクリーンエネルギー− 気象ブックス019
牛山 泉 著
世界にはさまざまな風が吹いています。ハリケーンもあり、台風もあります。心地よく肌を撫でてゆく春風もあれば、一瞬にして地上の全てを巻き上げる突風もあります。毎日の気象情報では気温、降水量の他に「風力・風向き」が予報されています。
風は気温や降水量に比べれば日々の生活にそれほど深い関わりはないように見えます。ところが、本書によると、風は私たちの生活に無縁なものではなくなります。日本には「○○風」とか「○○おろし」のように風に地域独特の名前が付いていたり、「風情がある」とか「風雅を好む」などのような風に関する言葉や、風に関する地名が多く……
漁業資源【2訂版】−なぜ管理できないのか−
川崎 健 著
水産資源管理の基盤となる理論として、漁業科学を構築し、国際協力の下での資源の合理的利用を提言、現状を反映させた改訂版。
【目次】
1. 資源の争奪戦
1-1 タラ通漁からタラ戦争へ-北大西洋の場合-
1-2 イカ・サバ紛争-日本では-
1-3 北太平洋のサケマスを巡って-日米ロの闘い
2. 資源変動-環境か漁獲か-
2-1 力学的資源管理思想の発生とそれを巡る論争
2-2 マイワシとニシンの変動
2-3 ペルー・アンチョビーとエルニーニョ
2-4 レジーム・シフト
2-5 北大西洋のマダラ資源の「崩壊」
2-6……
アジアのエビ養殖と貿易
多屋勝雄 編著
エビ養殖の盛んなアジアが抱える環境破壊・生産物の汚染・地域経済の摩擦問題と、エビ消費大国日本の輸入・流通・消費等養殖事情を解明。
第1章 アジアのエビ養殖
1.1 エビ養殖の展開と養殖池の分類
1.2 エビ養殖業の抱える問題
第2章 インドネシアのエビ漁業−日本への輸出が与えた影響−
2.1 エビトロール漁業の展開と冷凍エビ輸出
2.2 エビ漁業の展開
2.3 エビ産業の再編と冷凍エビ輸出構造の変化
2.4 日本への冷凍エビ輸出がエビ産業に与えた影響
第3章 「エコシュリンプ」と粗放養殖風景
3.1 対談「エコ……
さかな随談
金田禎之 著
本書の著者は、主として水産関係の法令に関する専門書を多く著してきたことで知られていますが、この本はそれらとは少し趣が違っています。半世紀にわたって水産行政と漁業の現場に立ち会ってきた著者が、そのなかで出会ったさかなにまつわる忘れられない出来事や事件の顛末をまとめたのが本書であり、酸性度の強い湖にウグイを移植する苦労話、全盛期の頃の捕鯨の様子、密漁の現行犯逮捕の話など、興味深い話題が多くあります。
また、これらの出来事や事件とともに、それぞれのさかなについて、名前の由来から種類、形態、分布、日本人の生活とのかかわり、漁具・漁法、利用・加……
水産・海洋ライブラリ9 ヘルスフード科学概論
矢澤一良 著
近年、食品関係者だけでなく一般の人々の間でも食と健康に対する意識が高まっています。EPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)といった言葉もすっかり定着した感があります。一方、食品開発の現場では消費者の健康志向に応えるべく、ヘルスフードの概念から特許戦略に至るまで総合的な食の知識が求められるようになってきました。
本書は、食品産業に携わる人が食と健康を考える上で必要となる知識や食品研究・開発のあるべき姿をまとめたものです。 内容は、食品産業の現状、予防医学の概念、臨床試験の組み立て方、機能性食品素材の探索等について……
二級・三級海技士(航海)口述試験の突破〈運用編〉【6訂版】
堀 晶彦・淺木健司 共著
【はしがき】より
本書は、三級海技士(航海)および二級海技士(航海)の免許を受けようとしている人たちを主な対象としてまとめた「運用」口述試験突破のための参考書です。
過去に出題された海技従事者のための学科試験(口述)の問題を幅広く集め、さらに今後の予想される問題も加えて編集してあります。
できるだけ理解しやすく、また覚えやすいように、各科目とも設問形式をとり、解答は箇条書で分かりやすく述べてあります。
設問によっては、説明の補足としてあるいは誤解のないように〔注〕を設けて内容の充実を図っています。
このたびの改訂においては、……
あわび文化と日本人 ベルソーブックス002
大場俊雄 著
あわびは、古くから日本人の生活と共にありました。縄文時代には交易品として、奈良・平安時代には貢物として、戦国時代は武将の出陣の儀式に使われるなど、時代によって様々な役割を果たしてきました。
本書は、そんな日本のあわび文化を詳しく紹介。あわびの生態から歴史、食文化、漁業などに至るまで幅広く取り扱っています。
これを読めば、「あわび」のすべてがわかります!
「はじめに」より
荒海の磯に付いているアワビをはがしとると、殻からあふれ出るように盛り上がった身を生きいきとくねらせる。アワビは貝類の中でとび抜けて肉量が多く、しかも食べ……