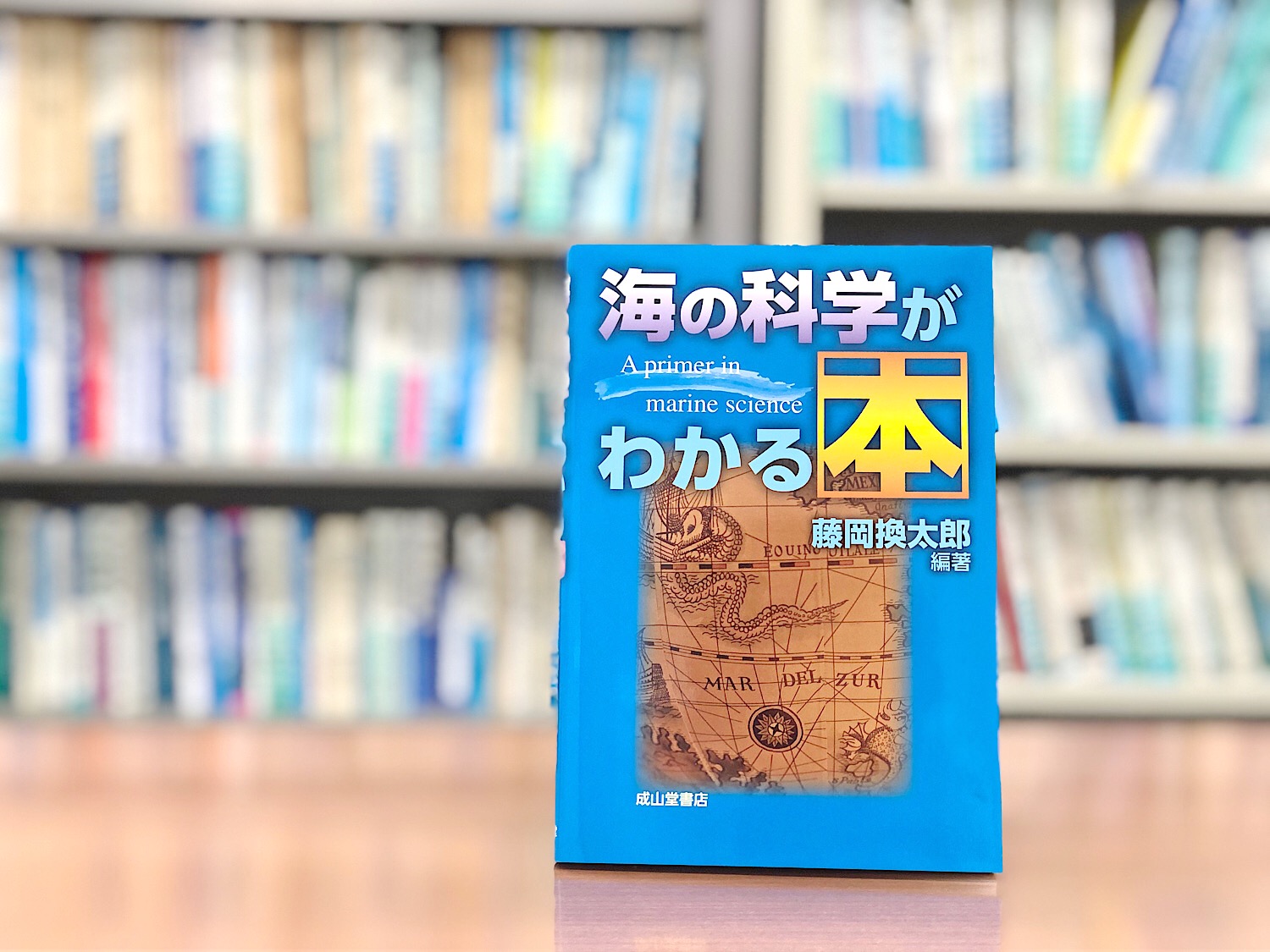『海の科学がわかる本』解説の第3回目は、地球上の大気の大循環について解説します。地球上の大気の流れは、刻一刻と変化しています。今回解説する第3章では、対流圏で起こる大気大循環の特徴を説明し、その原理に基づいて、海洋や海氷の変動がそれに及ぼす影響について解説します。北極海の氷が減ると、日本も異常気象に見舞われるのは何故でしょう?
第2章と地続きのような内容ですが、こちらは流体圏における大気の部分に注目した章になります。
はじめに
日本の上空には、季節により強弱はあるものの、常に西風(偏西風)が吹いています。北半球・南半球を問わず、対流圏の中高緯度に吹く風です。偏西風は季節や日により強さや位置が変化しており、言い換えれば「波動」として日々の天気や長期的な気候の変動にも密接に関係しています。
子午面循環と東西循環
空気は暖まると軽くなり上昇し、冷えると重くなり下降する性質があります。地球の大気に当てはめると、赤道付近で上昇して上空を極域まで移動して下降し、地表付近で赤道に移動するような南北鉛直循環(子午面循環)の存在を想像することができます。
しかし、実際に観測される対流圏の大気循環は子午面循環ではなく東西循環(中緯度西風ジェット)が勝っています。この東西循環を理解するためには、コリオリの力と地衡風の概念を理解する必要があります。
コリオリの力は物体の速さに比例し、高緯度ほど強くなります。地衡風はコリオリの力と気圧経度力が釣り合うように、等圧線に沿って吹いている風です。
低温である北極側は低気圧、高温である低緯度側は高気圧なので、北半球で北極を中心とする低気圧の周りを巡る西風は、高緯度側に向く気圧経度力と低緯度側に向くコリオリの力がバランスして吹く地衡風とみなすことができます。日本上空等気圧経度力の大きいところでは、強い西風による大きなコリオリの力がバランスしているのです。
一方、南北温度傾度とコリオリの力の弱い赤道付近の低緯度帯では、むしろ子午面循環が南北熱輸送の主な運び手となっています。
中高緯度大気循環場の大規模な波動
30年の平均をとると、北半球の高度場は蛇行していることが確認できます。このことは、同じ場所に停滞する波が存在することを示しています。北半球では日本上空、北米東岸、東欧の上空に気圧の谷が存在します。この波は惑星規模の大きさを持つのでプラネタリー波(惑星波)とも呼ばれています。
この波動はコリオリの力の緯度による違いに起因する波で、「ロスビー波」と呼ばれます(2章参照)。西に進む性質のあるロスビー波は時間平均を取ると消えてしまいますが、偏西風帯にあるロスビー波は、西風がロスビー波を東へ進めようとする力と打ち消し合うと、地理的に同じ場所に波動が居座ることになります。これを「定常ロスビー波」と呼びます。
海洋・海氷変動が大気循環場に及ぼす影響
《熱帯(海洋)の影響》
大気大循環場に影響を及ぼす海洋現象として最もよく知られているのが「エルニーニョ現象」です(第2章参照)。エルニーニョ現象は2〜6年に一度発生し、ピークは12月頃であることが多いため、北半球では冬の大気循環場や天候に影響を及ぼします。日本では暖冬になりやすい傾向があると言われています。
赤道域で通常は西太平洋にある海面水温の高い領域がエルニーニョ時には太平洋中央部に移動し、それに伴って滞留活動の活発な領域も移動します。これによってハドレー循環が局所的に強まり、亜熱帯域の下降風を強め海上に高気圧ができやすくなります。
エルニーニョ時には北太平洋中緯度に低気圧、カナダに高気圧、米国南東部に低気圧のような波列がしばしば形成され、これはPNAパターンと呼ばれます。エルニーニョによるハドレー循環が偏西風帯にかかる亜熱帯に高気圧偏差をもたらし、そこからは定常ロスビー波として北太平洋、更には北米方面へと伝わっているのです。
このように大気の一部に起こった循環場の異常が定常ロスビー波などで遠方に伝えられる現象を、「テレコネクション」と呼びます。月平均場で現れるような大気循環場異常の程度が強い場合は、しばしば異常気象をもたらします。
《中高緯度(海氷)の影響》
日本の北に位置するオホーツク海は世界で最も低緯度まで海氷が広がる海洋で、北海道もオホーツク海沿岸中心に冬季は海氷に覆われます。その要因のひとつは、冬のオホーツク海にはシベリアからの北寄りの季節風によって寒気がまともに入りやすい場であることが挙げられます。近年海氷は減少傾向にありますが、年による海氷勢力の変動も大きく、これは大気循環場の変動などにより、寒気の強さや入り方が変わるためと考えられています。
海氷分布の違いは、大気場にも影響を及ぼすと考えられています。海氷は大気と海洋の熱交換において断熱材として働くため、海氷の多少は大気への加熱源の分布を変えます。
しかし、実際の観測においては大気が海氷に及ぼす影響が強いため、観測データからその影響を検出することは困難です。モデルを用いた実験では、オホーツク海の海氷の多少は定常ロスビー波によって北米上空の大気循環異常を引き起こす可能性が示されています。
《中高緯度(海洋)の影響》
中緯度においては海氷変動のような大きな熱コントラストを形成できないため、中緯度の海洋→大気の影響の検出はより難しくなっています。しかし最近、北大西洋の西岸境界流であるメキシコ湾流が上空の大気循環場に影響を及ぼし得るという研究結果が発表されています。
夏季北極海の海氷減少がもたらす冬季極東の低温大雪
近年、夏季を中心に北極海の海氷域面積が大きく減少しています。このような夏の海氷減少に起因する異常気象の例として、日本等の極東ユーラシア各地に低音や大雪などをもたらす可能性についての研究を紹介します。
北極海の海氷の減少が高温・少雪ではなく低温・大雪をもたらすのには、定常ロスビー波が大きく関わっていました。冬に向かって海氷域が急速に拡大する11月頃を中心に、シベリア沿岸の西方に位置するバレンツ海の海氷が少ないと、断熱材が少ないため海洋は大きな大気加熱を持ちます。この加熱異常が定常的な強制となって定常ロスビー波を励起し、それがユーラシア大陸上空を南東方向に伝わり、12月にかけてシベリア高気圧を発達させます。そのため、極東各地に寒気が入りやすくなるのです。
この海氷減少が今後も続いた場合、アジア各地の冬はますます寒くなるのでしょうか?そうなった場合は熱の分布や輸送、更には大気循環場の状態(基本場)も変わってくる可能性があるため、大気場の平均的な状態そのものが変わる可能性があります。従って新しい基本場の元での振る舞いを考えなくてはならないのです。
おわりに
海洋・海氷が大気場に及ぼす影響と各地にもたらす異常気象について、「定常ロスビー波」の役割を中心に解説してきました。一般に大気の現象は同じ空間スケールだと海洋の現象に比べて遥かに早く応答・変化します。大気は地球上のすべてを覆っていますので、今日の大雪の原因が数日前に地球の裏側で起こった現象だということもあり得ます。
一方海洋の現象は重く緩慢ですが、じわじわと影響を及ぼします。時間が長い現象においては、海の影響の方がはっきり強く現れます。大気において数ヶ月以上の時間的スケールを持つ現象は、多くの場合海の影響だと考えられます。
今回は、海洋で起こる現象が大気に及ぼす影響について、主に大気に注目して解説してきました。夏に氷が少ないと大気に海の熱が多く伝わるため、冬に低気圧が発達し極東地域が寒くなるというメカニズムが、このような説明を受けるとよく理解できます。
「大気は早く、海は緩慢」、冬寒い家に帰ってきて暖房をつけながらコンロでお湯を沸かすとき、思い出してみようと思います。地球規模の時間的・空間的にダイナミックな変化と、自宅内でも見られる現象が繋がっていると思えるところが、科学の面白いところですね、
次回は、海洋における化学に迫ります。海の中では、二酸化炭素はどのような振る舞いを見せるのでしょうか。